不動産鑑定評価基準について、筆者が気になる部分を要約しました。
https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf
不動産の価格とは
不動産の価格とは、効用、相対的稀少性、有効需要の相関結合による経済価値を、貨幣額で表示したものです。以下に挙げるのは、価格形成要因です。
- 自然的要因
- 地質、地盤等の状態
- 土壌及び土層の状態
- 地勢の状態
- 地理的位置関係
- 気象の状態
- 社会的要因
- 人口の状態
- 家族構成及び世帯分離の状態
- 都市形成及び公共施設の整備の状態
- 教育及び社会福祉の状態
- 不動産の取引及び使用収益の慣行
- 建築様式等の状態
- 情報化の進展の状態
- 生活様式等の状態
- 経済的要因
- 貯蓄、消費、投資、国際収支の状態
- 財政、金融の状態
- 物価、賃金、雇用、企業活動の状態
- 税負担の状態
- 企業会計制度の状態
- 技術革新及び産業構造の状態
- 交通体系の状態
- 国際化の状態
- 行政的要因
- 土地利用に関する計画及び規制の状態
- 土地及び建築物の構造、防災等に関する規制の状態
- 宅地及び住宅に関する施策の状態
- 不動産に関する税制の状態
- 不動産の取引に関する規制の状態
- 日照、温度、湿度、風向等の気象の状態
- 街路の幅員、構造等の状態
- 都心との距離及び交通施設の状態
- 商業施設の配置の状態
- 上下水道、ガス等の供給・処理施設の状態
- 情報通信基盤の整備の状態
- 公共施設、公益的施設等の配置の状態
- 汚水処理場等の嫌悪施設等の有無
- 洪水、地すべり等の災害の発生の危険性
- 騒音、大気の汚染、土壌汚染等の公害の発生の程度
- 各画地の面積、配置及び利用の状態
- 住宅、生垣、街路修景等の街並みの状態
- 眺望、景観等の自然的環境の良否
- 土地利用に関する計画及び規制の状態
- 地勢、地質、地盤等
- 日照、通風及び乾湿
- 間口、奥行、地積、形状等
- 高低、角地その他の接面街路との関係
- 接面街路の幅員、構造等の状態
- 接面街路の系統及び連続性
- 交通施設との距離
- 商業施設との接近の程度
- 公共施設、公益的施設等との接近の程度
- 汚水処理場等の嫌悪施設等との接近の程度
- 隣接不動産等周囲の状態
- 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
- 情報通信基盤の利用の難易
- 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
- 土壌汚染の有無及びその状態
- 公法上及び私法上の規制、制約等
- 建築(新築、増改築等又は移転)の年次
- 面積、高さ、構造、材質等
- 設計、設備等の機能性
- 施工の質と量
- 耐震性、耐火性等建物の性能
- 維持管理の状態
- 有害な物質の使用の有無及びその状態
- 建物とその環境との適合の状態
- 公法上及び私法上の規制、制約等
- 敷地内における建物、駐車場、通路、庭等の配置
- 建物と敷地の規模の対応関係等建物等と敷地との適応の状態
- 修繕計画・管理計画の良否
- その実施の状態
- 賃借人の状況及び賃貸借契約の内容
- 貸室の稼働状況
- 躯体・設備・内装等の資産区分及び修繕費用等の負担区分
不動産の価格に関する諸原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 需要と供給の原則 | 財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まる。 財の価格は、その財の需要と供給に影響を及ぼす。 |
| 変動の原則 | 財の価格は、価格形成要因の変化に伴って変動する。 |
| 代替の原則 | 代替性を有する2以上の財が存在する場合には、相互に影響を及びして定める。 |
| 最有効使用の原則 | 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくもの)を前提として把握される価格を標準として形成される。 |
| 均衡の原則 | 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合 せが均衡を得ていることが必要。 |
| 収益逓増及び逓減の原則 | 単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。 増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。 |
| 収益配分の原則 | 土地、資本、労働、経営(組織)の各要素の結合によって生ずる総収益は、各要素に配分される。 |
| 寄与の原則 | 不動産のある部分が不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全体の価格に影響を及ぼす。 |
| 適合の原則 | 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その環境に適合していることが必要。 |
| 競争の原則 | 超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的には超過利潤を消滅させる傾向を持つ |
| 予測の原則 | 財の価格は、その財の将来の収益性等についての予測を反映して定まる。 |
不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価とは、不動産鑑定士が、不動産の経済価値(適正な価格現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値)を判定し、不動産の経済価値を貨幣額をもって表示することです。
鑑定評価の流れ
鑑定評価の流れは、次のとおりとされています。
- 基本的事項の確定(依頼者ヒアリング)
- 不動産の確認
実地調査、ヒアリング、資料確認によって確認する。
登記事項証明書、図面、写真、地図、一般的要因に係る資料、地域資料、個別資料、建設事例資料、取引事例資料、収益事例資料、賃貸借等事例 - 資料の検討
- 鑑定評価手法の適用
- 試算価格又は資産賃料の調整
- 鑑定評価額の決定
- 鑑定評価報告書の作成
基本的事項
対象不動産の確定
鑑定評価の対象となる不動産、権利を確定しなければなりません。
| 対象確定条件 | 説明 |
|---|---|
| 構成状態を所与として鑑定評価の対象とすること | |
| 独立鑑定評価 | 土地と建物があるのに、更地であるとして鑑定評価の対象とすること |
| 部分鑑定評価 | 土地と建物があるのに、その状態を所与として、構成部分を鑑定評価の対象とすること |
| 併合鑑定評価 分割鑑定評価 | 併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすること |
| 未竣工建物等鑑定評価 | 工事未完了の土地又は建物について、工事完了を前提として鑑定評価の対象とすること |
価格時点の確定
価格形成要因は時の経過により変動するため、不動産の価格は、その判定の基準となった日においてのみ妥当するものです。そのため、価格判定基準日(価格時点)を確定する必要があります。
求める価格の決定
求める価格は、通常は正常価格です。正常価格の前提となる合理的市場とは、次の要件を満たす市場をいいます。
- 市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入・退出が自由であること
- 市場参加者は、自己の利益を最大化するために次の要件を満たし、慎重かつ賢明に予測し、行動する
- 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機がない
- 取引成立のために必要な通常の知識や情報がある
- 取引成立のために通常必要な労力・費用を費やす
- 最有効使用を前提とした価値判断を行う
- 通常の資金調達能力がある
- 市場参加者の制約や売り急ぎ、買い進みを誘引するような特別な取引形態でないこと
- 相当の期間市場に公開されていること
| 価格の種類 | 内容 |
|---|---|
| 正常価格 | 現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格 |
| 限定価格 | 不動産の併合又は一部取得分割等の際、取得部分の限定市場に基づく市場価値を適正に表示する価格 ※市場が限定されるため、限定価格と呼ぶ。 ※借地権者の底地併合、隣接不動産の併合、経済合理性に反する分割などは限定価格 |
| 特定価格 | 法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で不動産の経済価値を適正に表示する価格 ※証券化対象不動産の投資採算価値、民事再生法に基づき、早期売却を前提とする価格、会社更生法又は民事再生法に基づき、事業の継続を前提とする価格を求める場合は特定価格 |
| 特殊価格 | 文化財など、一般的に市場性がない不動産について、利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格 |
分析
地域分析
地域分析とは、不動産がどのような特性のある地域にあるか、その特性が価格形成について全般的にどのような影響力を持っているかを分析し、判定することです。
個別分析
個別分析とは、個別的要因が、不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析し、不動産の価格の前提である最有効使用を判定することです。
典型的需要者がどのような個別的要因に着目して行動し、代替・競争関係にある他の不動産と比べて優劣・競争力の程度をどのように評価しているかを的確に把握することが求められます。
鑑定評価手法
鑑定評価手法には、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つがあります。
共通原則
一般的要因との関連
いずれの手法においても、常に一般的要因を考慮し、価格の妥当性を検討するために活用しなければなりません。
事例の収集・選択
建設事例、取引事例、収益事例などは、取引事情が正常なもの(合理的市場下のもの)であって、時点修正ができ、基本的に近隣地域の不動産について収集します。
事情補正
建設事例、取引事例、収益事例に特殊事情があり、価格等に影響があるときは、適切に補正(事情補正)しなければなりません。
時点修正
建設事例、取引事例、収益事例の時点が価格時点と異なり、価格水準に変動が認められる場合には、価格時点の価格に修正しなければなりません。
地域要因・個別的要因
建設事例、取引事例、収益事例は地域要因や個別的要因を反映しているため、必要に応じて要因の比較を行う必要があります。
原価法
原価法は、価格時点における建設資材や工法等による標準的な建設費(構造ごとの建築単価×床面積)と、引渡しまでに発注者が負担する通常の資金調達費用等が含まれる通常の付帯費用を加算した再調達原価について減価修正を行って試算価格(積算価格)を求める手法です。再調達原価の把握と減価修正を適切に行える場合に有効です。
直説法と間接法どちらを採用するかは、収集資料の信頼度に応じて判断します。
直説法とは、資材費と労働費(人件費)を調査したうえで、その地域の価格時点における単価を基礎とした直接工事費を乗じて間接工事費と請負者の一般管理費を加えて標準的な建設費を求める方法です。
間接法とは、近隣類似不動産の工事事例等から、間接的に再調達原価を求める方法です。
減価修正は、老朽化・偶発的損傷摩耗・破損・時の経過・自然的作用によって生じる(物理的要因)、建物と敷地との不適応、設計の不良、設備の不足、旧式化、設備の不足、設備能率の低下(機能的要因)、近隣地域の衰退、環境との不適合、市場性の減退(経済的要因)などの原価要因に基づき発生した減価額を、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用して求めます。
経済的残存耐用年数とは、価格時点において、用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じて、その効用が十分に持続すると考えられる期間です。
取引事例比較法
取引事例比較法とは、できるかぎり多数の取引事例のうち適切な事例の取引価格について、事情補正・時点修正を行い、地域要因の比較・個別的要因の比較をして算出した価格を比較考量して試算価格(比準価格)を求める手法です。
近隣地域・同一需給圏内の類似地域で、類似不動産の取引が行われている場合に有効な手法です。
収益還元法
収益還元法とは、収益事例を参考にしつつ、将来の期待純収益の現在価値の総和を算出して試算価格(収益価格)を求める手法です。
市場性を有しない不動産を除き、自用の不動産であっても賃貸を想定し、すべての不動産に適用すべきものとされています。もちろん、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業用不動産の価格を求める場合は特に有効です。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。
引用元:国土交通省「不動産鑑定評価基準(平成26年5月1日一部改正)」27頁
純収益とは、不動産(の所有者)に帰属する適正な収益のことで、一般に年間総収益から年間総費用を控除したものです。償却前純収益、償却後純収益など、総収益と総費用の把握の仕方によって異なります。
純収益は、過去の推移、将来の動向を慎重に分析して適切に求めなければなりません。
総収益=賃料+保証金等運用益+権利金等運用益+償却額+駐車場使用料+その他の収入
賃貸用不動産についてDCF法を適用する場合、賃料稼働率、貸室稼働率の変動に留意しなければなりません。
総費用=減価償却費(ただし償却前純収益を求める場合は除く)+維持費+管理費+修繕費等+固定資産税+都市計画税+損害保険料+その他諸経費等
DCF法を適用する場合、大規模修繕費等の費用の発生時期留意しなければなりません。
還元利回り((インカムゲイン+キャピタルゲイン)/投資金額)は、割引率と同様に不動産の収益性を表すものです。
還元利回りは収益性を表す反面、将来の期待純収益に影響を与える要因の変動予測の不確実性、その予測自体の不確実性が含まれます。
合理的市場においては、高い収益が確実に見込める場合には価格も高くなります(需要が高い)が、高い収益が不確実であるときは価格は抑えられる(需要が低い)からです。
つまり還元利回りは、収益予測に係る不確実性(リスク)を織り込んだうえで、その資産にいくら投資できるかどうかから求められる収益性(利回り)といえます。一般的には、リスク・リターンの関係です。
還元利回りは、他の資産の収益性・運用利回りと密接に関連します。不動産の場合は、地域要因や個別的要因によって異なる傾向にあります。
直接還元法では収益価格、DCF法では復帰価格の算定時に、1期間(通常1年間)の純収益から価格を直接求める際に使用します。
還元利回りを求める方法は、次のとおりです。
- 類似不動産の取引事例(取引事例利回り)をもとに取引時点・取引事情・地域要因・個別的要因の違いに応じた補正を行う
- 借入金の還元利回り(年賦償還率=年間返済額/借入金額)と自己資金の還元利回り(返済額控除後の自己資金利回り)を、構成割合によって加重平均する
※金利、期間、借入比率などの標準的な借入条件と自己資金還元利回りが適切に算定できる場合に信頼性が高いが、自己の還元利回りの算定は困難 - 土地の還元利回りと建物の還元利回りを、構成割合によって加重平均する
- 割引率をもとに、純収益の変動率を考慮する
割引率は、還元利回り((インカムゲイン+キャピタルゲイン)/投資金額)と同様に不動産の収益性を表し、収益価格を求めるために用いるものです。
性質は還元利回りとほとんど同じですが、見込んだ純収益や復帰価格は与えるため、その分の不確実性(リスク)は除かれます。時間待機分の不確実性とでもいえるでしょうか。
ただし、割引率を求める方法は取引事例利回り、借入金と自己資金の還元利回りは適用できますが、土地と建物の還元利回りは適用できません。割引率に限って、債券等の金融資産の利回りに投資危険性、非流動性、管理困難性、資産安全性としての個別性を加味して求めることは可能です。
直接還元法
直接還元法とは、通常1年間の純収益を還元利回りによって還元して収益価格を求める方法です。
DCF法
DCF法とは、連続複数期間の純収益と復帰価格の現在価値の総和を収益価格と求める方法です。

不動産鑑定評価書
不動産鑑定評価書は、不動産の鑑定評価の成果が記載された専門的文書であるとともに、国家資格者である不動産鑑定士が作成した信頼性のある文書です。
不動産鑑定評価書には、次のような事項が記載されています。
- 鑑定評価額
- 鑑定評価の対象となった土地・建物などの表示
- 依頼目的その他鑑定評価の条件
- 鑑定評価額の基準年月日と鑑定評価を行った年月日
- 鑑定評価額の決定の理由
- 不動産鑑定士の対処不動産に関する利害関係など
実際の不動産鑑定評価書では、鑑定評価額の決定の理由が詳細に記載されるため、理由の部分が大半を占めます。
査定と鑑定の違い
| 比較項目 | 査定 | 鑑定 |
|---|---|---|
| 基準 | 特になし | 不動産鑑定基準 |
| 主体 | 不動産会社 | 不動産鑑定士 |
| 費用 | 無料 | 数十万円 |
| 速度 | 1週間程度 | |
| 算出価格 | 高め | 低め |
| 用途 | 売出し価格の参考 | 適正な価格の証明 ※公示地価 ※都道府県地価 ※裁判所 ※税務署 |
なお、不動産鑑定士が不当な鑑定を行った場合、不動産鑑定士は資格を失う可能性があります。
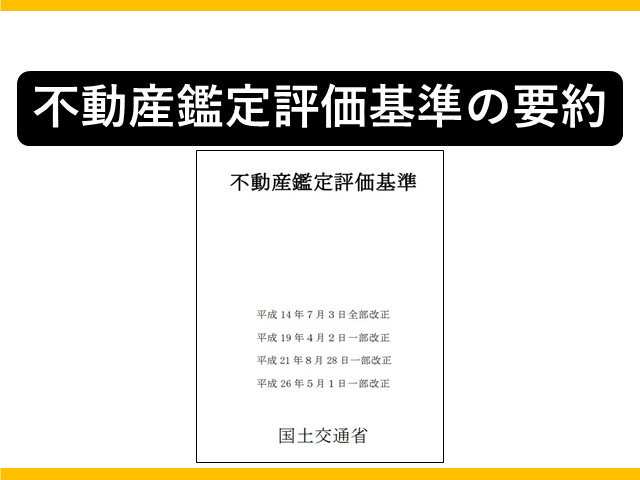


コメント